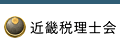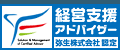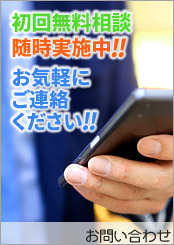







2010年11月15日(月)
| 今月の税務情報 vol.18 「中小企業者の少額減価償却資産」 |
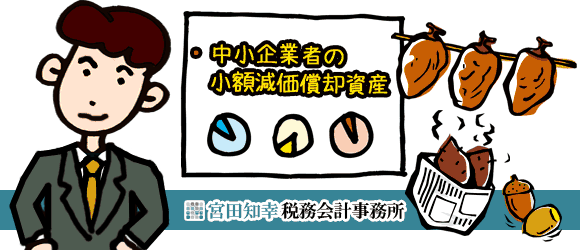
今月の税務情報は、「中小企業者の少額減価償却資産」についてご案内します。
■ 制度の概要
中小企業者の少額減価償却資産とは、少額減価償却資産(使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満の資産)や一括償却資産(取得価額20万円未満の資産で、一括して3年で償却)とは別に、取得価額30万円未満の減価償却資産については、取得時にその全額の損金(必要経費)算入を認める制度です。
この制度は、青色申告の適用を受けている中小企業者だけを対象としており、平成24年3月31日までに、取得した資産が対象となっています。
中小企業者とは、資本金1億円以下の法人、または、従業員数1000人以下の個人事業者をいいますが、大企業の子会社等は除かれています。
■ 対象資産の選択方法
中小企業者の少額減価償却資産は、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産、一括減価償却資産は除きます)であれば、自由に選択することができます。
ただし、一事業年度(個人については1年)について、300万円が上限となっています。この上限規定は、たとえば、取得価額26万円の資産を15個取得した場合、合計額390万円のうち、300万円を認めるということではなく、少額減価償却資産を単位としていますので、個々の少額減価償却資産について選択し、その合計額が300万円以下でなければならないということです。
したがって、26万円の資産であれば、11個選択(合計額286万円)することはできますが、12個選択(合計額312万円)することはできないことになります。
■ 判定方法
30万円未満であるかどうかの判定は、その資産の通常1単位として取引される単位ごとに行い、取得価額には、購入代価だけでなく付随費用も含まれることになります。
消費税等の取り扱いについては、会社の経理方法によって異なります。税込み経理を採用している場合には、消費税等の額も含めて30万円未満になるかどうか判定することになりますし、税抜き経理を採用している場合には、消費税等の額は含めないで判定することになります。
たとえば、購入価額298,000円(税別)の資産を取得した場合、税抜き経理であれば、30万円未満で少額減価償却資産に該当することになりますが、税込み経理であれば取得価額312,900円(=298,000円×1.05)で、30万円以上となるため少額減額償却資産には該当しないことになります。
■ 特例適用の手続き
中小企業者の少額減価償却資産の適用を受けるためには、確定申告書に別表十六(七)「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の添付が必要です。
個人については、青色申告決算書の減価償却費の計算欄に、措置法28条の2第1項の適用をしていること、その取得価額の合計額、明細は別途保管している旨を記載し、明細書を別途保管していれば、明細書の提出を省略できます。
来月も「税務情報」をお届けします。お楽しみに。